 |
|
|||||
| 観音寺山を愛する会事務局:〒521-0226 滋賀県米原市朝日156-6 TEL(0749)55-1053 観音寺所在地:〒521-0226 滋賀県米原市朝日1342 TEL(0749)55-1340 |
 |
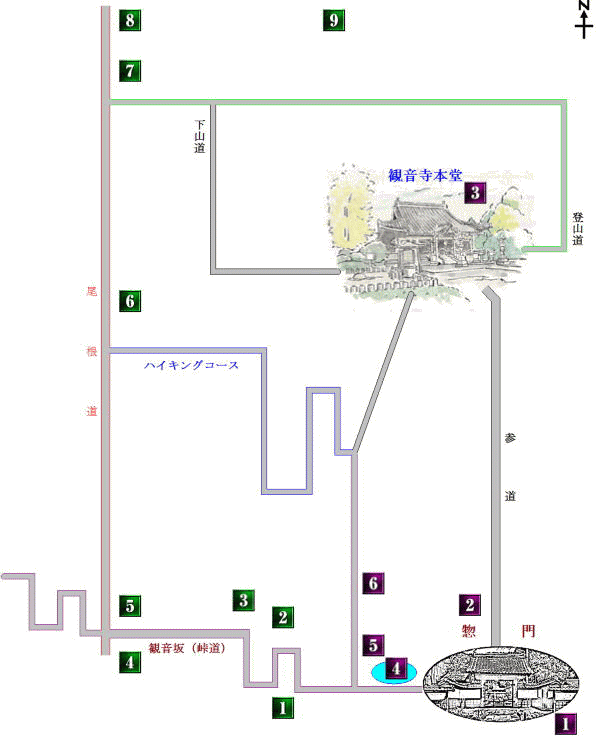 |
常夜灯 | |||||
| 惣門前の灯籠は、江戸中期建立。「観せ音」の文字一字に一升の米が入る、近江随一という石造文化財である。 | ||||||
| 惣 門 | ||||||
| 秀吉が城主であった長浜城の裏門を、観音寺の惣門とした。 | ||||||
| 観音寺本堂 | ||||||
| 貞和3年(1349年)に伊吹山(小弥高)に在した観音寺が、山を下りて現在の地に移る。暦応元年(1383年)に天台宗となる。 伊吹山四大護国寺(観音寺・弥高寺・大平寺・長尾寺)の一寺であり、三朱沙門安祥上人が開墓した。 |
||||||
| 蓮 池 | ||||||
| 昔は、池全面に蓮の花で美しい池であったが、改修後は蓮も少なくなった。 夜になると、本堂の台門紅梁の龍がこの蓮池に水を飲みに来たといわれる。 |
||||||
| 石田三成水汲みの井戸 | ||||||
| 秀吉が観音寺山に鷹狩に来た際、観音寺の丁稚であった三成がお茶を差し上げた時(三献の茶)に水を汲んだ井戸。 三碗三温の茶で秀吉に見込まれ家来となる。 |
||||||
| 後鳥羽院上皇腰掛の石 | ||||||
| 後鳥羽天皇が上皇になられ名越に行幸のおり、観音寺へ度々参詣されたとき休息のため腰をかけられた石である。 | ||||||
| 峠地蔵参詣途中御手洗場 | ||||||
| 観音坂頂上に鎮座されている峠地蔵に参詣する際にこの手洗場で身を清めた。 | ||||||
| 鏡 岩 | ||||||
| 約、長さ5m、巾3mの岩で、鏡の如く映るこの岩に旅人が自分の姿を写し、身支度を整えて峠を越したといわれる。 | ||||||
| お化け岩 | ||||||
| 鏡岩で髪の結い直しや化粧をしている人に嫉妬し、お化けとなって出て旅人を困らせたといわれる。 | ||||||
| 読誦回向の搭 | ||||||
| 大乗妙典一千部読誦回向。吉祥院珍翁が一千部読誦後、袈裟を岩にかけたその日からお化けが出なくなったといわれる。 | ||||||
| 峠 地 蔵 | ||||||
| 2体の地蔵は、朽木の殿様が家来に申し付けて、旅人が安全に山越えをして旅ができるよう念じて安置された。 | ||||||
| あ ず ま や | ||||||
| 平成16年に城跡まで行く途中休憩するために建てられた。 | ||||||
| 鐘 堂 | ||||||
| 昭和初期、観音寺昭道和商が梵鐘を寄進。村人総出で横山城跡に運び上げ建立した。 | ||||||
| 横 山 城 跡 | ||||||
| 横山城は浅井長政の命により、遠藤直経が永禄4年(1561年)に築城した。 最大の目的は織田信長の動きを監視するためで、長政は元亀元年(1570年)に再度修・増築するが、その年秀吉が長浜城に移り廃城となる。 |
||||||
| 横 山 | ||||||
| 臥竜山ともいわれ、村居田(旧山東町)が頭で竜ヶ鼻、能登瀬(旧近江町)が尾に当たる。 | ||||||
| ■■■ あづまやから見た 琵琶湖 ■■■ | ||||||
 |
||