 |
|
|||||
| 観音寺山を愛する会事務局:〒521-0226 滋賀県米原市朝日156-6 TEL(0749)55-1053 観音寺所在地:〒521-0226 滋賀県米原市朝日1342 TEL(0749)55-1340 |
| 峠地蔵 峠地蔵尊玉石 峠首落ち地蔵の慈悲 朽木の殿様 横山城築城 横山城の最期 北近江から生れた武将 |
| 観音坂道中(朽木街道) |
| 峠地蔵(蓮池から362m) |
| 観音坂の頂上に二体のお地蔵さんがお堂の中にお祭りしてあります。 |
| 古いお地蔵さんで、朽木の殿様が家来に命じてここに安置され旅人を守ってくださいと祈願されたそうです。 |
| この通りは、朽木の殿様が参勤交代のために江戸を往復された道で、これを朽木街道と名付けらました。 |
| 近江路の朽木街道で一番の難所が観音坂で、山頂での休憩に家来が殿様に「この坂は一番の難所であり、しかも |
| 追剥が出て旅人が困り果てています。」と耳打ちしたのが地蔵さんの安置の始まりでした。 |
| それ以後は、お地蔵さんのお守りで安心して峠越えができるようになったそうです。 |
| お嫁さんを大切にするお婆さんが突然足腰が痛んで歩くことが出来なくなったため、そのお嫁さんが七日間この峠地 |
| 蔵さんにお参りして願をかけ一生懸命お祈りをしました。 |
| 八日目の朝、お嫁さんがお婆さんの様子を見に行くと、正座して峠地蔵に向かって合掌し「ありがたや、ありがたや」 |
| と言って頭を幾度となく下げていていたので、どうしたのと尋ねたら、「昨夜夢の中で、お前宅の嫁が七日間この峠ま |
| でお婆さんの足腰が治りますようにとお参りに来た。今日が願い事満願の日で朝になったら快復している。嫁を一層 |
| 大切にせよ。」と言われて目が覚めたら、足腰の痛みが嘘のように無くなったとお婆さんは答えたそうです。 |
| 峠地蔵尊玉石 |
| 重軽さんは古いお地蔵さんが安置され祭られている所にはほとんどといっていい程おられます。重軽さんは一種のお |
| 地蔵さんです。 |
| お地蔵さんにお願いをして願い事が通じた場合は軽く持ち上がり、通じない場合は重くて持ち上がらないところから重 |
| 軽さんと呼ぶようになったそうです。 |
| 玉石はお地蔵さんの身代わりです。昔の人は、自分の患部を治すためにお地蔵さんにお参りをして玉石を撫でてから |
| 自分の患部を撫で「どうか治してください」とお願いをしていました。 |
| 玉石を撫でることによってお地蔵さんを撫でたことになるのですから、玉石は地蔵尊の台座に安置されています。 |
| 観音坂の峠地蔵さんは向かって右は玉石です。平成14年4月にお堂を据え付け、土中より取り出し台座を作成し安置 |
| しました。 |
| 峠首落ち地蔵の慈悲 |
| 昔の大原野といえば大原の荘のやや西寄りに途方もない広い原野でした。林といっても巨木ばかりで日中といえども |
| 薄暗い所が多いので小動物(狐・狸・ムササビ等)がたくさん棲んでいました。 |
| ある日、上夫馬(朝日)に庄屋の孫作さんが小作者の田圃の見回りに駕篭に乗って出かけました。 |
| いつもの通り大原野の地蔵前で休憩をしようと駕篭から降りると、小作の一人茂作じいさんがポカンとして座っている |
| ので、庄屋さんが、「茂作なにをしているのか」と尋ねると、「実は、古狐がお地蔵さんに供えてある団子を食べている |
| ので、後ろから思い切り鍬で殴りました。手応えはあったのですが狐の姿はなくお地蔵さんの首がポロリと下に落ちて |
| いるので、びっくりしてどうしようかと思いながら落ち込んでいるところへ庄屋様がおいでになりました。庄屋様どうした |
| らよいか教えてください。」と、泣きながら懇願してきました。 |
| 庄屋さんは「もともと大原野を往来する人の無事を願って建立したお地蔵様とお堂だ。このお地蔵様は誰にでも慈悲 |
| 深いお救いの本尊だ。私に任せて帰りなさい。」と言って茂作を帰しました。 |
| こうして茂作を帰した後、庄屋さんはお経をあげてもらい落ちた頭を元の位置へ載せて答拝しました。 |
| 古狐はお咎めもなく今迄通り供物をお地蔵さんから頂いて、悪いことはその後一切せず夜になると他の狐を集めてワ |
| イワイ、ガヤガヤとお地蔵様のお守りをしたそうです。 |
| 人間であれ動物であれ、公平に慈悲深く見守られたお地蔵様でした。 |
| 戦中から戦後になって殆ど開拓され、畑や宅地となった現在、森林組合から市場の一部に少し面影が残ってる程度で |
| す。 |
| お地蔵様は庄屋(夫馬宅屋敷内)の家に、六体のお地蔵様と並んで正面から向って一番右側に今でも安置されていま |
| す。このお地蔵様は旅人の無事を願って庄屋さんが安置されたものです。 |
| 肩掛け地蔵については後日面白く書かれたものと思われます。 ※肩掛け地蔵は実存しません。 |
| 朽木の殿様 |
| 峠地蔵さんを家来に命じて安置して祭られた朽木の殿様についてお話します。 |
| 佐々木信綱の次男の高信は、父の信綱から高島郡の分領を受けて高島氏を名乗りました。高信には2人の子があり |
| 長男の泰信が家督を継ぎ、次男の頼綱が高島郡朽木庄を分封されて朽木氏の祖となりました。 |
| 朽木庄を領した頼綱には4人の子があり、長男の頼信は横山庄を領して横山氏となり、次男の氏綱は田中庄を領して |
| 田中氏となりました。 |
| 秀吉の家来となり後関ケ原合戦で敗残の石田三成を捕らえた田中吉政は氏綱の子孫です。 |
| 三男の義綱は、父の家督を継いで朽木氏となり子孫は三家に分かれ朽木村の本家は四千二百三十石となります。 |
| 近江の朽木氏が信長にも適当に仕えて保身につとめ、関ケ原役にも土壇場で西軍から東軍に寝返って保身を全うし |
| ました。朽木氏は信長・秀吉・徳川と代々上手に仕えて保身につとめました。 |
| 徳川時代に入って、参勤交代で江戸を往復する朽木の殿様がお駕篭で通られた道から朽木街道(旧伊吹町春照神社 |
| 前北国街道交差点まで)と名付けられました。 |
| 大原庄(旧山東町)は佐々木信綱の嫡男である太郎重綱を粗としている重綱。重綱は父の信綱と共に承久の乱に北 |
| 条方に加わり宇治川で武功をたてたが、信綱は重綱を廃嫡し次男高信(高島佐々木)、三男泰綱(六角佐々木)、四男 |
| 氏信(京極佐々木)に領地を分領しました。 |
| 重綱は僧となって慈浄と名乗っていたが、父の信綱の死後黒衣を脱して弟の六角泰綱と遺領を争い、鎌倉に訴えて坂 |
| 田郡大原庄を確保して大原氏を名乗りました。 |
| このことにより朽木の殿様と大原氏とは深い縁故(佐々木家)で結ばれています。 |
| 佐々木信綱 ⇒ 高信 ⇒ 頼綱 ⇒ 義綱 ※頼綱から朽木の殿様となります。 |
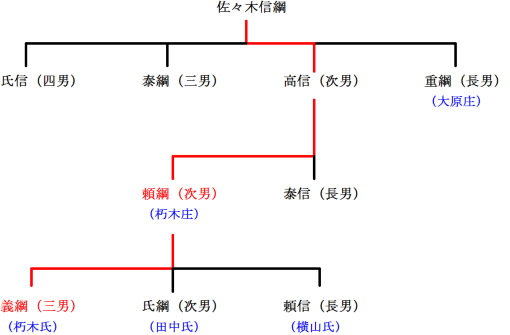 |
| 横 山 城 |
| 横山城築城 |
| 横山城は、浅井長政の命によって遠藤直経が永禄4年(1561年)に築いたものです。 |
| これは織田信長の動きを監視するのが最大の目的で観音寺本堂の西北の一番高い山頂に築かれた城でした。 |
| 長政は元亀元年(1570年)5〜6月にかけて再度修築及び増築をして、東は北国道、南は中山道彦根方面まで、西は長 |
| 浜、北は浅井・伊香を見渡す要所とした主城をはじめ北尾根数百メートルの小高い頂に見張りの北城があり、北城の |
| 付近には米蔵がありました。その近くには館跡と思われる所が数多くあります。 |
| 南尾根数百メートルにも南城があったといわれ、馬駆け場と伝えられる平らな所も残っています。 |
| これだけの増築・修築をしたのは織田信長の湖北侵入に備えてのことですが、それにしても城には瓦は使っていない |
| ようです。おそらく屋根は桧皮葺きか杉皮葺きかだと思われます。 |
| また、頂上には深い穴がいくつもあって猪落としの為だと言われていて、井戸も現在残っています。 |
| 築城については小谷城を攻めてくるのを見張る役目の城で、後に秀吉が長浜城に移るまではこの城におり、長浜城に |
| 移り横山城を廃城しました。 |
| 現在城跡には夫馬孫作さんが観音寺の玉泉院で僧となって寒中でも僧衣に草履を履いて修行托鉢に長浜方面へ毎 |
| 日出掛け信者の方と城跡に昔を偲んで梵鐘をあげ、観音様を戦って討ち死にした霊を慰めるために祭りました。 |
| この梵鐘は当時の朝日区民の大人子供共々ソリに乗せて、戸田朝蔵氏の音頭で本堂横から「ヨーイソゥレー、ヨーイ |
| ソゥリャー」と大きな掛け声をかけながら城跡まで引っ張って運んだそうです。(昭和12年) |
| なお、本堂の東から城跡までの登山道と城跡から南廻り下山道には観音様(石像)三十三体が道端に祭られています |
| これも僧が托鉢で信者からの寄進で安置されたのが今日までの状況です。 |
| 僧は昭和17年1月3日 享年63歳にて歿されました。(無量寿昭道和尚) |
| 横山城の最期 |
| 野村橋南岸の「姉川古戦場」と大きく書かれた標柱の辺に佇むと、北西に遠く小谷山が聳え、南には近く横山が見える |
| 。小谷本城と横山支城の距離は姉川を挟んで5.5kmである。 |
| 元亀元年(1570年)5〜6月にかけて浅井長政は織田信長の湖北侵入に備えて新たに横山城を修築・増築し、大野木 |
| 英俊(旧山東町大野木)、三田村国定(旧浅井町三田)、野村直元・直次(旧浅井町野村)などに守らせた。 |
| 6月24日、信長は難攻不落の小谷城から浅井勢を姉川におびき出し、一挙に雌雄を決しようと二万余騎の全軍こぞっ |
| て横山城を攻め立てた。 |
| 横山城に立て篭る浅井軍は三千余騎であるが、一騎当千の兵揃いである。 |
| 逆茂木、塹壕に土塁、更に、要所に巨大な空壕を巡らせた縦深配備の山岳陣地を盾に、鉄砲を放ち、矢・石を飛ばし |
| 持ち場を死守して一歩も退かなかった。炎天続きで敵味方とも汗だくになって三日三晩攻防戦を展開したが城は落ち |
| なかった。 |
| しかし、6月28日の姉川合戦で浅井、朝倉連合軍は総崩れとなって退散した。信長は兵をまとめて竜ヶ鼻(旧山東町村 |
| 居田)の本陣に戻り、柴田勝家森可成、木下秀吉に横山城を攻めさせた。城内の将兵は、姉川の敗報を聞いて愕然と |
| 色を失った。 |
| 水の手を断たれて炊飯もできず、白米で馬を洗って城にはまだ水があるように見せかけた。秀吉は死武者相手の力 |
| 攻めでは味方の損害も大きいので和平策を試みた。城門近くに馬を進めた秀吉は大音声で呼びかけた。 |
| 「城内の諸士に物申す。生命をかけて城を守られるご様子、秀吉はほとほと感服致した。されど戦いはすでに終わった |
| 。もともと織田殿は浅井家とは親戚でござる。されば、戦いに勝ちながら小谷の城を攻めずに引き上げなさる。諸士も |
| 一刻も早く城を空けて小谷の城へ帰られよ。我々は誓って邪魔立ては致さぬ。」 |
| 城内ではこれを聞いて戦意を失い逃亡兵が続出し、遂に城将も城を明け渡した。古老の話によれば、横山城跡には、 |
| 昔から奇奇怪怪な出来事が数多く起きるという。 |
| 深夜、観音坂を通ると人柱として埋められたという女巡礼の啜り泣きが聞こえ、本丸跡の松ノ木の傍らに痩せ衰えた |
| 武士の幽霊が現れ、西の丸米蔵跡には米を洗う幽霊が出るなどと誠しやかに語り継がれている。 |
| なお、城を退去するとき一武将は |
| 朝日射す 夕日輝く木の下に 小判千両埋めおく |
| という埋蔵金のありかを示す歌をのこした。 |
| 横山には石田三成の莫大な黄金が眠り、鳥羽上の峠(横山トンネル)にも金の鶏が埋められているという。 |
| 北近江から生れた武将 |
| 戦国武将の出生伝承には謎が多いが、秀吉については特に異説が多いようです。湖北地方にも昔から数々の秀吉伝 |
| 説が語り継がれています。 |
| 【 曲谷・草野説 】 |
| 初代慈海(比叡山修行僧)の妻(大政所)は東草野谷、曲谷村の生まれの娘で、七曲谷を越えた上草野庄中村の草野 |
| 家に預けられ、大津坂本の宿坊の炊事係として雇われていた。 |
| 二人は恋仲となり何時しか身ごもり叡山を追放された。その後郷里の草野家に身を寄せ屋敷裏の小屋で男の子を産 |
| み、この子を半介と名付けた。この子が後の秀吉である。 |
| 半介は、8〜13歳まで隣の鍛冶屋で奉公をした。父慈海は大垣に出て就職したが家族を呼び寄せるいとまもなく死亡し |
| た。母は尾張中村の人と再婚するが夫は行方不明となり、母と半助は尾張中村に移住した。 |
| 秀吉は尾張中村で生れたことになっており、これが通説となったようである。 |
| 豊臣秀吉(旧浅井町草野) 石田三成(長浜市石田町) 佐々成政(旧余呉町下余呉) |
| 片桐旦元(旧浅井町須賀谷) 増田長盛(旧びわ町益田) 脇坂安治(旧湖北町丁野) |
| 大谷刑部(旧余呉町小谷) 小堀遠州(長浜市小堀) 島 左近(旧近江町飯) |
| 遠藤高虎(甲良町在土) 黒田長政(旧木之本町黒田) 明智光秀(多賀町佐目) |
| 多羅尾光俊(信楽町) 蒲生氏郷(日野町) 蜂須賀小六(尾張) 真田幸村(信州上田) 宇喜多秀家(岡山) |
| 徳川家康(三河国秦氏の子孫) |
| 姉川本流の山間部や支流草野川の谷合を中心とする北近江(湖北)から戦国武将が輩出している。 |
| 中国の東晋安帝元興2年(403年)融道王弓月君が「120県民」を率いて日本に帰化した。この秦人の一族が近江にも |
| 来住し、姉川流域に湯次郷・宮部郷・大井郷などを開拓したという。姉川に伏樋を造り水田を作って素晴らしい集落を |
| 形成した。 |
| 仏教伝来の際は蘇我氏と共に秦河勝をはじめ、秦一族は容仏派聖徳太子を奉じて排仏派物部氏と戦い、物部守屋を |
| 小谷山麓に追い詰めて大勝したが、その後太子一族が滅ぼされて失脚し湖北の拠点も抹殺され、わずかに山間の谷 |
| 合に山の民として流浪していた。以来千年の間闇に葬られていた秦一族の怨念が戦国時代に爆発して秦一族の大集 |
| 団が、同じ秦氏の秀吉を支えて天下取りの偉業を達成させた。 |
| 戦国期の湖北の山麓から何故秀吉をはじめ多くの英傑が出たかという謎の一端がこれで解明できるのではないだろう |
| か。信長は秦氏の子孫ではないので、秀吉・家康・光秀等にうまく利用されて殺されたのだという。 |
| ページのトップに戻る |